食品機械のメンテナンスは必要?基本やメンテナンス時のポイントを紹介
機械のメンテナンスは、食品工場において欠かせない業務の一つです。
しかしながら、定期的なメンテナンスを怠ると、機械の故障やトラブル、最悪の場合はラインの停止につながりかねません。
また、機械のトラブルにより、食品の製造中に異物が混入してしまった場合には、食品メーカーとしての信頼が損なわれるリスクもあるのです。
そこで本記事では、食品機械のメンテナンスの重要性や考え方、メンテナンスを円滑に進めるポイントを紹介します。
なぜ食品機械にメンテナンスが必要なのか?

食品機械の定期メンテナンスは、食品製造の現場で欠かせない取り組みです。
なぜなら、機械の不調や劣化を放置すると、異物混入や衛生トラブル、さらには生産ラインの停止といった重大なリスクを招いてしまうためです。
製品への異物混入や機械による事故が起これば、消費者の安全を脅かすだけでなく、企業の信頼低下や製品の回収・損失といった大きな打撃を受ける可能性があります。
例えば、清掃や点検を怠ったがために機械部品が破損して食品に混入した事例や、重要な包装機が突然故障して出荷ができなくなったケースも実際に報告されています。
食品機械のメンテナンスは安全と生産性を守る土台です。このような事態を防ぐためにも、食品機械に対する計画的なメンテナンスが必要不可欠となります。
異物混入・事故防止
食品機械のメンテナンスでもっとも重要な目的の一つが、異物混入や機械事故の防止です。
清掃不良で溜まった汚れや、摩耗したパッキン・ベルトの破片が食品に混ざれば、消費者に危害を及ぼす可能性があります。
また、部品の破断や落下による作業者の怪我など事故につながることも考えられます。日頃から機械を点検・整備し問題箇所を見逃さないことが、異物混入や事故を未然に防ぐ鍵です。
稼働停止による生産ロスの防止
生産ラインの稼働停止による損失を防ぐためにも、食品機械のメンテナンスは重要です。食品製造ではラインが止まると、生産計画が狂い納品に遅れが生じたり、製品供給が滞って売上に影響を及ぼしたりします。
故障が発生してから慌てて修理を手配する「事後対応」では、部品調達や技術者の到着までに長時間ラインが止まってしまう可能性もあります。その間、生産途中だった製品を廃棄せざるを得ないケースもあり、大きなロスとなります。
例えば、長年使用している充填機のモーターが突然故障すれば、その代替品の調達に数日〜数週間かかり、その間生産停止となりかねません。実際に、特殊な部品の故障で新品入手に数か月を要し、製造スケジュールに深刻な影響が出たケースも報告されています。
定期的なメンテナンスで摩耗部品を事前に交換し、異常の兆候を見逃さず対処しておけば、こうした突発的なラインストップを未然に防ぐことが可能です。
法令・HACCP・FSSC22000との関係
食品機械のメンテナンスは、法令や食品安全規格の上でも求められている重要な取り組みです。
食品衛生法の改正によりHACCPに沿った衛生管理が原則すべての食品事業者に義務化されましたが、その一般衛生管理項目の中で、設備機器の適切な保守管理と定期清掃は基本要件となっています。
つまり、機械を定期的に洗浄・点検し正常に稼働する状態を保つことが、法令順守と食品安全確保の両面で求められているのです。
実際、HACCPやFSSC22000の運用では、機械設備の洗浄・点検手順を文書化し、その実施記録を残すことが求められます。監査の際には「〇〇機はいつどのように点検し、結果はどうだったか」といったログが確認され、適切に保守されているかチェックされます。
仮にメンテナンスを怠ったことで異物混入事故や製品不良が起これば、行政からの指導や認証の一時停止・取り消し等のリスクさえあります。このように、食品機械のメンテナンスは自主的な品質管理であると同時に、法的要求や国際基準への適合という観点からも欠かせない要素なのです。
食品機械のメンテナンスの基本

食品機械のメンテナンスは、日常点検から定期整備、さらには必要に応じたオーバーホールまで段階的に実施されます。この章では、メンテナンスの方式を作業頻度や深さごとに分類し、それぞれの内容と担当の目安を紹介します。
メンテナンスの分類(予防・予知・事後)
食品機械の保全は大きく分けて予防保全・予知保全・事後保全の3種類に分類できます。
- 予防保全:機械が故障する前に決められた間隔で点検・部品交換を行う手法で、日常点検や月次・年次点検など計画的なメンテナンスが該当
- 予知保全:機械の状態を常に監視して異常の兆候(予兆)を検知し、故障が起こる前に対処する手法
- 事後保全:機械が故障してから修理を行う対処法
この中で意識したいのは予防保全です。予防保全は日常的なメンテナンスを指しており、使用時間や経過期間に応じて潤滑油を注油したり、消耗部品を交換する作業が予防保全にあたります。
一方でなるべく避けたいのが事後保全です。事故保全は、故障やトラブルが起きてからの事後対応となるため、生産体制に影響を及ぼしやすいです。
また、事故対応を行なっている時点で生産に何らかの影響が出るため、このような状況下ではまともに生産できる可能性は低いでしょう。
このため、食品機械メーカーが目指すべきメンテナンス体制は「予防保全」となります。
主な対象部位と点検項目(部品別)
食品機械のメンテナンスの主な対象部位と点検項目は以下の通りです。
| 機械 | メンテナンス箇所 | 交換の目安となる部品 |
|---|---|---|
| コンベアなど搬送装置 | ・ベルトの摩耗・張り具合、ローラー回転状態の確認 ・ベルトの亀裂・ほつれ、偏摩耗の有無 ・駆動モーターやチェーン駆動部の潤滑状態、異音・過熱チェック ・粉や食品片の堆積防止のため定期清掃 | ベルト 駆動チェーン モーター部品 |
| ミキサー | ・羽根の磨耗・ガタつき確認 ・羽根の欠け・曲がり・コーティング剥離 ・軸受け(ベアリング)の異音・振動 ・使用後の分解洗浄とパッキン類の劣化確認 | 羽根(ブレード) ベアリング パッキン類 |
| 包装機 | ・シール部(熱板・シーラー)の温度・圧着面の状態 ・シール用ヒーター・テフロンシートの寿命確認 ・包装フィルムのカッター刃の切れ味 ・光電センサー・重量検知センサーの作動確認と清掃 | シール用ヒーター テフロンシート カッター刃 |
| 充填機 | ・ノズルやバルブ類の詰まり・摩耗 ・充填ノズルの固着物確認 ・Oリングやパッキンの劣化・亀裂 ・計量シリンダー・ピストンの摩耗点検 ・使用後の分解洗浄 | ノズル リング パッキン ピストン |
| 包あん機 | ・成形部ユニット(口金・金型)の磨耗・位置ずれ ・カッターや絞り出し部の摩耗 ・カッター刃や成形プレートの切れ味 ・スクリューやギアの異音・詰まり確認 ・異物混入防止のための分解清掃 | カッター刃 成形プレート スクリュー ギア |
機械ごとの重要部位を把握し、消耗品はメーカー推奨のサイクルで交換することが安定稼働への近道です。
ベルトやパッキン、フィルター類などのスペア品はあらかじめ常備し、異常を発見した時点で速やかに取り替えられる体制を整えておくと安心です。
食品機械のメンテナンス費用と契約の考え方

機械の保守体制を構築する際には、コスト面の計画も重要です。
ここでは、メンテナンスにかかる費用の一般的な目安と、スポット対応(都度依頼)と保守契約(定期契約)の違いについて紹介します。
あらかじめ必要経費を把握し計画しておくことで、予期せぬ出費に備えつつ、どこまで予防保全に投資すべきかの判断材料にもなるでしょう。
日常の点検整備にどの程度予算を割き、緊急時の出費をどう抑えるかを検討する材料にしてください。
メンテナンス費用の目安
メンテナンス費用は、まず消耗部品の定期交換にかかる費用は比較的小さな出費で済むことが多いです。
例えば、コンベアベルト1本の交換費用は部品代が数千円~1万円程度から、作業工賃を含めても数万円規模でしょう。パッキンやOリングといったゴム部品も一個数百円〜千円台と安価で、予防交換しても負担は少ないです。
これに対し、モーターや制御基板など主要部品が故障すると高額になります。製造装置のモーター交換では部品代だけで数十万円、制御装置全体の修理ともなれば場合によっては100万円以上の出費になるケースもあります。
また、機械が故障した際には修理費だけでなく、停止期間中の生産ロスも経済的損失となります。こうしたリスクを平準化する方法の一つが保守契約です。
メーカーや保守サービス会社と年間契約を結ぶと、定期点検や簡易な修理がパッケージ化されたプランを利用でき、年間費用が予め確定します。
契約内容にもよりますが、年間契約料は機械1台あたり数十万円程度から設定されることが多く、複数回の点検と緊急対応の優先サポートなどが含まれます。
スポット対応のみで運用するより、一括契約で割引が適用される場合もあり、結果的にコストを抑えつつ安心感を得られるでしょう。
ただし、小規模事業者では契約費用が負担に感じられる場合もあるため、自社の機械台数や重要度に応じて検討が必要です。
事後保全ではなく予防保全を
食品機械のメンテナンスは、費用面からも「壊れてから直す」より「壊れる前に手を打つ」予防保全の姿勢が重要です。
事後保全中心の運用では、前述のように一度の故障対応で多額の費用が発生したり、生産停止による売上損失が重なったりするリスクがあります。突発の故障対応は、部品を緊急輸送したり夜間対応したりと通常よりコスト高になる傾向も否めません。
一方、予防保全に注力すれば、計画的な部品交換や点検によって大きなトラブルを未然に防げるため、結果的にトータルコストを低減できる可能性が高まります。
「壊れたら直す」文化から「壊れる前にケアする」文化へシフトすることが、安定稼働と費用削減の両立につながります。
食品機械のメンテナンスを円滑に進めるポイント
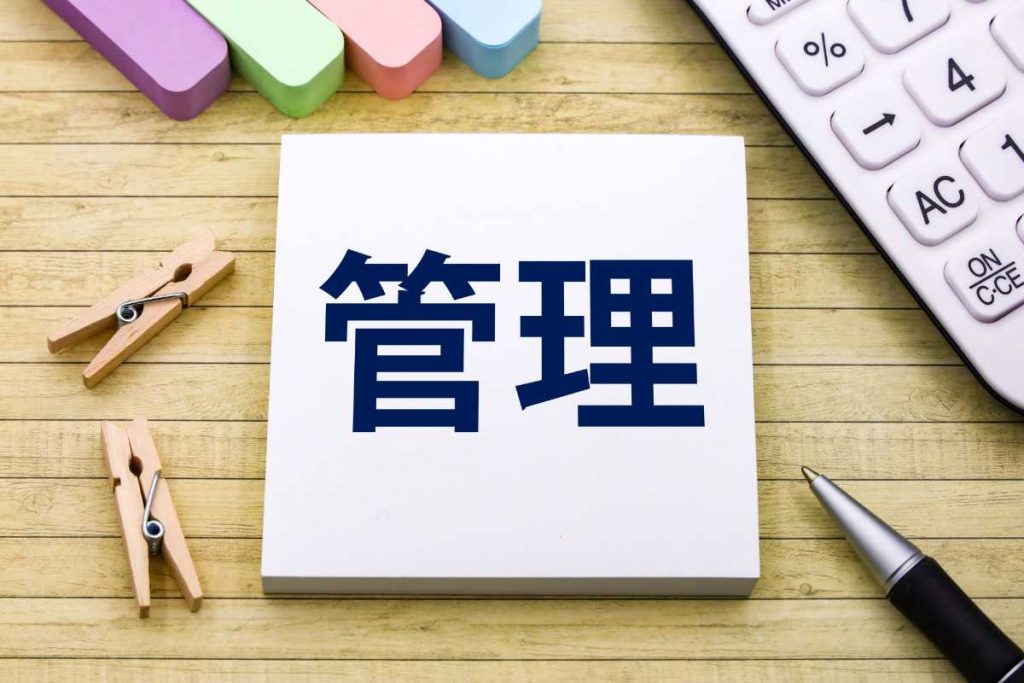
ここからは食品機械のメンテナンスを円滑に進めるポイントを紹介します。
メンテナンスのマニュアルを作成する
スムーズに確実なメンテナンスを実施するためには、自社の設備に合わせたメンテナンスマニュアルを整備することが重要です。マニュアルには、機械ごとの点検項目や手順、頻度を具体的に明記します。
例えば「毎日稼働前に〇〇の油量を確認」「週に1度は〇〇を分解清掃」「半年ごとに〇〇部品を交換」のように、誰が見ても同じように作業できるチェックリスト形式にすると分かりやすくなります。
また、安全に作業するための注意事項(「必ず電源を切ってから作業する」等)や、異常を発見した際の報告フロー(「上長と保全担当に連絡し、日誌に記録」等)も記載しましょう。
マニュアルを作成しておけば、新任の担当者でも迷わず必要な点検が行えるため、属人化を防ぎメンテナンス品質を均一に保てます。
なお、マニュアル作成にあたっては各機械のメーカーが提供する保守点検要領や取扱説明書を参考にし、自社の現場に合わせてカスタマイズすると効果的です。また、一度決めた手順も定期的に見直し、現場で気付いた改善点があれば随時追記・修正して、より良い内容へアップデートしていきましょう。
機械を動作させる担当者にマニュアルを周知する
実際に日々機械を扱う担当者は、小さな異常に真っ先に気付ける立場にあります。その担当者自身が「どの箇所を点検すべきか」「どんな兆候を見逃してはいけないか」を理解していれば、トラブルの芽を早期に摘むことが可能です。
例えば、稼働前点検の際に普段と違う音や振動に気付いたらマニュアルに沿って報告・対処する、といった習慣を身につけてもらいます。そのためには、定期的な研修や朝礼での注意喚起などを通じて、マニュアル記載事項を周知徹底しましょう。
新しい機械を導入した際も、メーカーから操作説明を受けるだけでなく、保全のポイントについても担当者が学び、社内マニュアルに反映させることが大切です。現場全体でメンテナンス意識を共有できれば、問題発生時の初期対応も迅速になり、大きなトラブルへの発展を防ぎやすくなります。
よくあるトラブル事例と未然に防ぐ方法
ここからは食品機械のよくあるトラブルや未然に防ぐ方法を紹介します。
異物混入につながる部品摩耗の見逃し
機械部品は少しずつ摩耗・劣化していくため、日常的に状態を監視していないと限界に達するサインを見逃しがちです。そのまま使用を続けて部品が破断すると、破片が製品に混入してしまう恐れがあります。
実際、ある菓子工場ではミキサーの攪拌羽根が長年の使用で薄く摩耗していたにも関わらず交換されず、最終的に一部が折れて生地に混入し、金属片入り製品の回収騒ぎとなった事例がありました。
このような事故を防ぐには、日頃から消耗部品の限界厚みや使用時間を把握し、メーカー推奨の交換時期を守ることが肝心です。
また、摩耗が進むにつれて普段と異なる振動や音が発生する場合もあるため、現場スタッフがそうした兆候に気付いたらすぐ報告・対応するよう教育しておくことも重要です。
ライン停止を引き起こした例と再発防止策
もう一つ頻繁に聞かれるトラブルが、設備故障による生産ラインの停止です。
パン工場のコンベアの減速機からオイルが微量に漏れているものの、日常清掃で見落とされていたケースの場合、やがて潤滑油切れとなった減速機が焼き付き故障を起こし、ラインが半日以上ストップしてしまう、ということも考えられます。
再発防止策としては、設備の下に油滴や粉の溜まりがないか日々確認する習慣をつけ、少しでも異常を察知したら運転を止めて点検することです。また、重要な予備部品をストックしておき、万一故障しても交換にすぐ入れる体制を整えることも有効です。
同様に、センサーの不良や配線トラブルでラインが停止した事例もありますが、これらも日常点検で配線の緩みやセンサーの汚れをチェックし、異常があれば早めに交換・清掃することで予防できます。
まとめ
食品機械のメンテナンスは「トラブルが起きてからでは遅い」という点を忘れてはなりません。異物混入や機械故障といった問題が一度でも発生すれば、製品回収による信用失墜や生産ロスなど、取り返しのつかない損害に直結します。
そうした事態を避け、品質と生産を安定的に維持するためには、日頃から計画的なメンテナンス体制を構築しておくことが何よりも重要です。定期点検や予防保全にしっかり取り組めば、結果として機械寿命が延び、部品交換や修理にかかるコストも長期的に削減できます。
食品製造現場において、メンテナンスは縁の下の力持ちです。トラブルが起きないのが当たり前です。その当たり前を支える地道なメンテナンスこそが、長期的な事業の成功と安全で高品質な食品を安定供給することに直結します。
株式会社コバードは、食品を包み込む包あん機をはじめとし、発酵生地の包成機を開発・提供しており、メンテナンスサービスも提供しています。お客様の食品製造を支えるメーカーとして100年以上運営してきた弊社の技術力は他社のメーカーにまけません。それは単なる機械の提供にとどまらず、導入後の安定稼働を支える「長期的な伴走力」にあります。
食品製造ラインでは「壊れにくい機械」だけでなく「安心して任せられるサポート体制」が不可欠です。コバードは自社で培ったノウハウと経験に基づき、導入から日々の稼働・メンテナンスまで一貫してサポート。お客様が「本業である食品づくり」に集中できる環境を提供しています。
詳しい製品ラインナップや導入事例は、ぜひ「コバードマシン一覧」をご確認ください。







