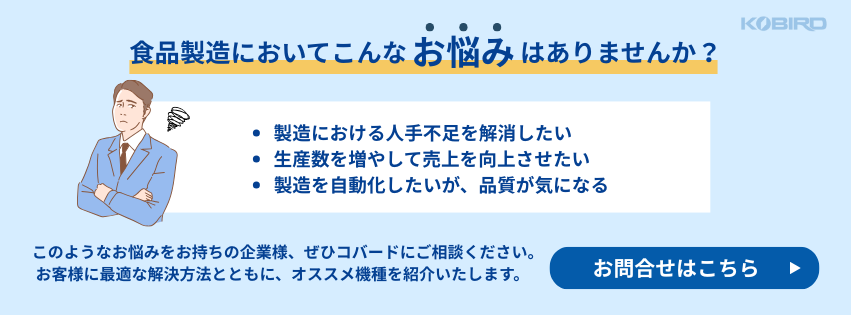グミを作る機械とは?導入のメリットやビジネス展開案を紹介
グミ製造機とは、グミキャンディの製造工程(原料の調合から成型・冷却まで)を自動化し、安定した品質で大量生産するための専用装置です。
手作業でグミを作る場合、温度管理や形状の均一化に手間がかかり、生産量にも限界があります。
しかし、機械を活用すれば原料の混合・加熱から型への充填、冷却・固化までの工程を連続的に行うことで効率のよい製造・生産が可能です。
そこで本記事では、グミを作れる機械の紹介とともに、活用のメリットや生産商品にあった機械の選び方を紹介します。
グミを作る機械とは?基本の仕組みと種類

グミ製造には「混合(調理)」「成型」「冷却」「乾燥」といった複数の工程があり、各工程に対応する機械が必要です。
これらを適切に行ってこそ安定した品質のグミができますが、全て手作業で行うのは非効率です。そこで、専用機械で各作業を正確かつ連続的に進めて効率化しています。
| 工程名 | 工程の内容 |
|---|---|
| 材料の混合・調理 | ・ゼラチン、糖類、水飴、香料・着色料などの原料をミキサーや加熱釜で混合 ・ゼラチンが完全に溶けるまで加熱し、シロップ状のグミ生地を調製する |
| 成型(注入) | ・調理した液状グミ生地を型に流し込む ・複雑な立体形状には、回転式金型を使用するロータリー成形機が活用され、高精度で緻密な形状のグミ製造も可能 |
| 冷却 | ・型に充填されたグミ生地を冷却して固める ・一般的には成型後に冷却トンネルで急速冷却することで、ゼラチンを凝固させて弾力のある食感に仕上げる |
| 乾燥 | ・グミ内部の水分を飛ばして、食感と保存性を高める ・スターチレス(ノンスターチ)製造機では、乾燥工程を省略し、成型機内の冷却装置によって製品化が可能 |
このように各工程に特化した機械を組み合わせることで、原料投入から製品化までグミ製造をスムーズに行えます。それぞれの機械が連携するラインによって、人手では難しい精密な制御と大量生産を両立できるのです。
グミ製造を機械化するメリット

グミの生産を機械化を導入する前に、事業者にとってどんな影響があるのかを知りたいところだと思います。
ここからは、業務効率・品質・コスト・市場対応の観点から核心を押さえて解説します。
生産効率向上で生産数が大幅アップ
グミ製造を機械化する最大のメリットは、生産効率が飛躍的に向上することです。
機械を導入すれば人手による作業よりもはるかに高速で連続的な生産が可能になり、短時間で大量のグミを作れます。機械なら24時間体制での稼働も容易です。
繁忙期の増産や急な大口注文にも余裕を持って応えられるようになり、効率化によるコスト削減効果も期待できます。
衛生管理と品質管理の向上
グミ製造を機械化すると、衛生管理と品質管理が飛躍的に向上します。
温度・時間・配合を機械が自動制御するため、人手によるばらつきが無くなり、製品の味・食感・見た目にムラが生じません。
また、人の手で直接触れる工程が減ることで、異物混入や衛生面のリスクも大幅に抑えられます。
例えば、人が作業をする場合、材料の混ざり具合や成型量にばらつきが出がちですが、機械ならそれがありません。加えて、人の手を介さないことで微生物汚染のリスクも減り、HACCPなど衛生基準の順守にも有利です。
このように機械化によって品質のばらつきを抑え、衛生管理を徹底できるため、安全で安定した製品供給につながります。消費者に常に同じ美味しさと安心を届けられる点も、機械化の大きな利点です。
市場変化への迅速な対応とイノベーション力の向上
グミ製造の機械化は、市場のニーズに合わせた新商品への迅速な対応力を高め、イノベーション(製品開発力)の向上にも寄与します。
これは、機械を使うことで様々な形状・フレーバーのグミを比較的容易に製造でき、小ロットの試作品も効率よく作成できるからです。
金型や設定を変更するだけで、新しい形のグミをすぐに試作できますし、一台の機械で単色はもちろん2色やストライプ模様のグミまで作ることも可能です。
また、従来は大量生産でしか採算の取れなかった商品も、自動化による効率アップで小ロット生産が採算ラインに乗りやすくなり、ニッチなニーズにも応えやすくなります。
その結果、消費者の好みや市場トレンドに素早く応え、新たなグミ商品を次々と生み出していく原動力となるのです。
グミ製造機の選び方|導入前に押さえるべき3つのポイント

購入や導入を検討している人が失敗しないよう、選定のチェックポイントを解説します。
生産量と対応ロット数
時間あたりに必要な生産量(処理能力)を満たす機械かどうかは最優先で確認しましょう。また、自社が対応したいロット規模にマッチするかも重要です。
「大量生産したいのに小型機では追いつかない」一方で「少量多品種なのに大型機ではオーバースペックでコスト高になる」といったミスマッチを避ける必要があります。
導入前に「毎時何kg(何個)の生産が必要か」「最小ロットはどれくらいか」を洗い出し、候補機種のスペックと照らし合わせた上で機械を選びましょう。
例えば1時間に100kgの生産能力がある機械なら、一日8時間稼働で800kg程度のグミが作れます。逆に月産数百kg程度であれば、コンパクトな機種でも十分対応可能です。
生産量の将来的な増減も見据え、適度な余裕を持った能力の機械を選ぶと安心です。
成型方式(ドロップ式/ロータリー式など)
グミの形状や作りたいデザインによって、適した成型方式の機械を選ぶことも大切です。
一般的なドロップ式(デポジター式)の機械は、液状のグミ生地を金型に流し込んで成型する方式で、様々な形に対応でき汎用性が高いです。
多色のグミや内部に酸味粉を入れるタイプなども、ノズルの工夫で同じライン上で製造できます。
一方、ロータリー式の成形機は回転する金型でグミ生地をプレスして成型する方式で、複雑な形状・デザインのグミ製造に適しています。生産速度も速く高精度ですが、専用の金型設計が必要になるためコストは高めです。
この他にも押出し式など特殊な方式もありますが、自社商品の形状や質感に合わせて最適な方式を選びましょう。
材料の多様性と清掃性
グミ製造機を選ぶ際は、その機械が扱える原料の種類や清掃のしやすさも重要なチェックポイントです。
製造したいグミによってはゼラチン以外の原料(ペクチンや寒天など)を使用したり、コラーゲンやビタミンなど特殊な添加成分を混ぜたりする必要があります。
機種によって対応できる材料や調理温度の範囲が異なるため、自社のレシピに合った機械を選ぶことが大切です。
また、食品製造では衛生維持のため頻繁な洗浄が欠かせないため、パーツの着脱が簡単か、洗いやすい構造かといった清掃性も考慮すべきです。
取り扱うグミの配合に対応でき、日々のメンテナンスに無理のない機械を選ぶことで、安定した生産と衛生管理を両立できます。
導入までの流れと運用ポイント
導入ステップ・メンテナンス方法・ランニングコストまで、運用に必要な実務を網羅します。
導入までのスケジュール
グミ製造機導入の一般的なスケジュールは、試作テストから始まり、正式発注・設置・稼働開始まで段階を踏んで進められます。
機械選定では実際に狙い通りの製品が作れるか確認するプロセスが重要で、大型機械の導入には準備や製造に時間がかかるためです。
導入までの主な流れは次のとおりです。
- ニーズの確認と相談: まず自社で必要な生産量やグミの仕様を整理し、メーカーや代理店に相談する
- 試作依頼と評価: 候補機種が決まったら、メーカーに試作品の製造を依頼し、自社レシピでグミを試作してもらい、味や食感・形状が狙い通りかを確認
- 正式発注と仕様確定: 試作結果に納得できたら導入機種を決定し正式発注します。機械の詳細仕様(サイズ、付帯設備、金型デザイン等)を詰め、見積金額と納期を確定
- 製造・納品準備: メーカー側で機械の製造・組立が行われます(通常、製作に数ヶ月を要します)。並行して設置場所のレイアウト変更や電源・配管等の準備を進める
- 据付・立ち上げ: 完成した機械が工場に搬入され、据付工事を行い、メーカー技術者立ち会いで試運転と操作研修を実施し、安全に稼働できる体制を整える
- 本格稼働開始: 試運転で問題がなければ本番生産を開始し、初期は製品品質や機械の調子を注意深くモニタリングし、必要に応じメーカーに調整を依頼する
試作から設置完了まで余裕を持って計画することで、スムーズな立ち上げが可能になるでしょう。
メンテナンス・部品交換の頻度と費用
グミ製造機導入後は、メンテナンス計画も立てておく必要があります。安定稼働させるためには、日常の清掃だけでなく、消耗部品の定期交換や専門技術者による点検が欠かせません。
そのため、機械部品の交換頻度や保守費用を把握し、継続的な運用に備えましょう。適切にメンテナンスを行わないと、生産中のトラブルで予期せぬコストやダウンタイム(稼働停止)が発生する可能性があります。
定期的な点検スケジュールを立て、メーカーとも連携してケアすることで、予期せぬ故障を防ぎ、生産ラインの安定稼働とコスト管理につながります。
グミ製造ビジネスの可能性と展望|販売戦略にも注目
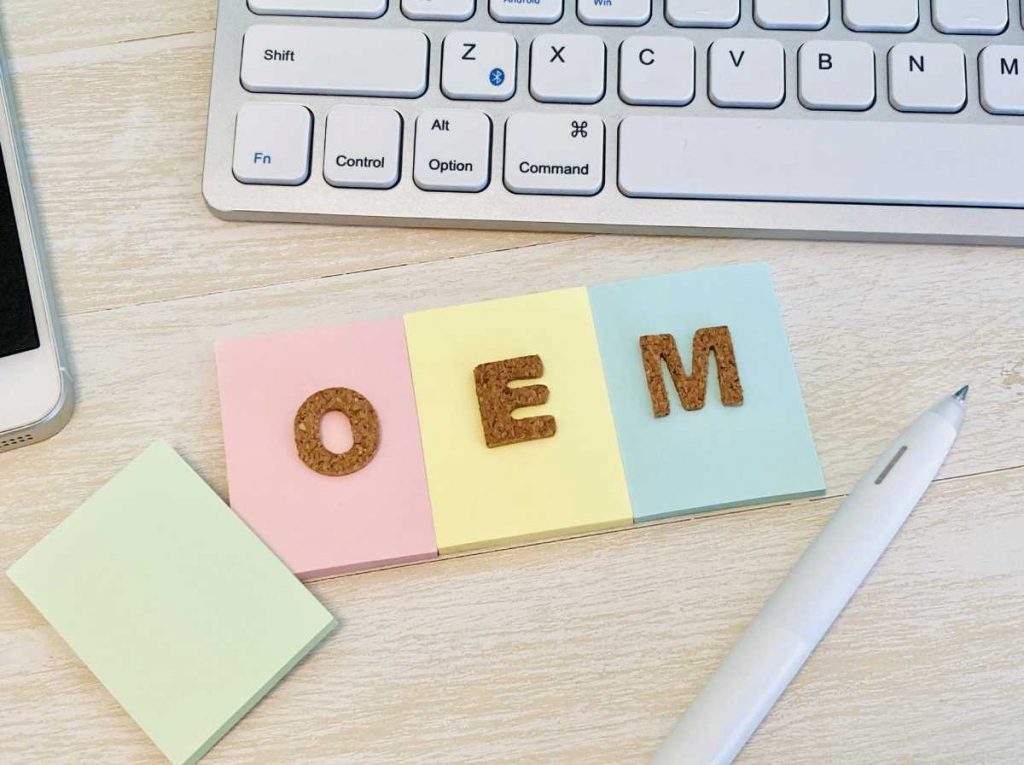
グミ製造の内製化で得られるメリット、OEM展開やブランド化までを解説します。
グミのOEMやPB(プライベートブランド)展開
グミ製造機を自社で保有すると、OEM(受託製造)やPB(プライベートブランド)展開といったビジネスチャンスが広がります。
自社工場でグミを生産できれば、自社ブランド商品を展開できるだけでなく、生産設備を持たない他社からの受託製造(OEM)を請け負うことも可能になるためです。
例えば、お菓子メーカーが自社ブランドのグミ菓子を新たに発売したり、健康食品メーカーがサプリメントグミをPB商品として販売したりするケースが増えています。
それら企業は製造設備を持たないことも多く、代わりに製造してくれるパートナーを求めています。このとき自社でグミ製造機を持っていれば、そうしたニーズに応えて新たな収益源を得ることができます。
実際、市場では小ロットからOEM生産に対応する製造会社も登場しており、柔軟な受注生産が可能になっています。さらに、自社設備でOEMを手掛けることで、稼働していない時間帯を有効活用し工場の生産効率を上げることもできます。
スモールスタートで始めるグミ事業
グミ製造ビジネスは、小規模な設備投資からでも十分に始めることができます。需要に合わせて無理のない規模でスタートすれば、初期費用を抑えつつ市場の反応を見ながら事業を拡大できるからです。
大型ラインを持たなくても、小型の業務用グミ製造機やセミオートの機械を活用すれば少人数・小スペースで生産が可能です。
初めはネット販売や店舗での少量販売からスタートし、ファンを増やしながら徐々に生産量を拡大することも可能です。
小規模設備なら生産ロットを柔軟に調整できるため、在庫リスクを抑えつつ季節限定商品やコラボ商品などにも挑戦しやすい利点があります。また、機械が小さい分、メンテナンスや運転コストも低く、少ない売上でも黒字を出しやすい点も魅力です。
なお、中古機の活用やリース契約を利用すれば、さらに初期負担を抑えることも可能です。
このようにスモールスタートでグミ事業を始めれば、過度な投資リスクを避けつつ着実にビジネスを育てることができます。まずは身の丈に合った規模で始め、需要の拡大に応じて設備を追加導入していくことで、無理なくグミビジネスを成長させていけるでしょう。
株式会社コバードが提供するグミ製造に使える機械
| モデル | AR-330-Ⅲ |
|---|---|
| 全幅 | 1,744mm |
| 奥行 | 975mm |
| 高さ | 1,921mm |
| コンベア高さ | 505mm |
| 電気容量 | 2.4KW |
| ホッパー容量 | 28リットル(外皮側) 16リットル(内包・芯具側) |
| 製品重量 | 2~50g |
| 生産能力 | 4,800~22,000個/時 ※製品重量により異なります |
コバード社の生地連続包あん機 AR-330 は、小型の菓子を効率よく成形するための業務用マシンです。
職人の「手もみの動き」を再現する特許技術の成形羽根を搭載し、小さなな食品を均一かつ高速に量産できます。
操作パネルにはカラー液晶タッチスクリーンを採用しており、設定変更も直感的で簡単です。ホッパーの高さも低めに設計されており、原料投入がしやすく、工具不要で部品が着脱できる構造です。
また、大福・団子・あんドーナツなど幅広い用途に活用され、グミ製造にも高精度な成形力が活きるため、安定品質と生産効率の向上が期待できます。
よくある質問(FAQ)
ここからはグミの製造機械に関するよくある質問を紹介します。
導入費用はどのくらいですか?
小型機なら数百万円程度、大型フルライン設備では数千万円に及ぶ場合もあります。機能や付属設備によっても変動するため、詳細はメーカーへの見積もり依頼が確実です。
設置にどれくらいのスペースが必要ですか?
例としてAR-330は全幅1.7m×奥行1.0m×高さ1.9m程度のスペースを要します。冷却装置や原料調理設備も含めたライン設置には周辺スペースの確認も重要です。
機械の操作は難しくないですか?
最新機種はタッチパネル操作で直感的に扱えます。基本操作を覚えれば1〜2名で運転可能で、導入時にはメーカーによる研修も行われます。
お手入れ(洗浄)はどのくらいの頻度で、どのように行いますか?
基本的に毎日洗浄を行います。部品は着脱式で、ステンレス製・温水洗浄可の設計が主流です。洗浄作業は慣れれば30分〜1時間程度で完了します。
まとめ
グミ製造の機械化について、その仕組みから導入のポイント、さらにはビジネス展開まで幅広く解説してきました。
手作業では難しかった大量生産や品質均一化も、専用機械を導入することで可能になり、生産効率と商品クオリティを飛躍的に高められます。
機械選びの際は生産量・成型方式・対応材料・清掃性などを総合的に判断し、自社ニーズに合った一台を見極めましょう。
導入にあたっては試作テストや段階的な計画が成功のカギとなり、導入後も定期メンテナンスを欠かさず行うことで機械を長く活用できます。
グミというお菓子は世代を超えて愛されており、今後も技術革新による新しい展開が期待されています。グミ市場はこれからも拡大が見込まれ、ユニークな商品や機能性グミへのニーズも高まっています。
自社でグミ製造機を稼働させれば、そうした市場の動きにタイムリーに対応でき、新商品開発や新たな事業機会につなげることができるでしょう。ぜひ本記事のポイントを参考に、グミ製造の機械化とビジネス展開にチャレンジしてみてください。