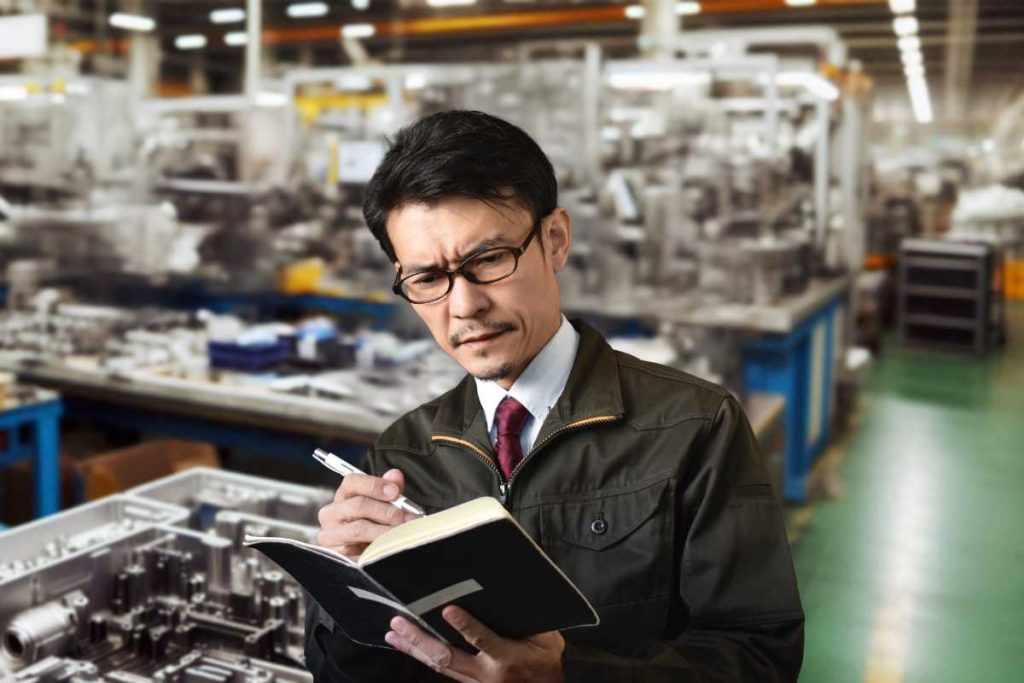包あん機は小型で十分?生産能力や対応食品を紹介
「大型機はオーバースペックだけど、手作業には限界がある」
そのギャップを埋めるのが小型包あん機です。
コンパクトでも毎時数百〜千個クラスを安定成形できます。
省スペース運用や多品種少量の段替えに強く、歩留まりと生産性を同時に引き上げてくれます。
そこで本記事では、小型包あん機の紹介とともに、対応食品や生産能力、設置寸法や向いている現場を解説します。
弊社で提供している小型ながらも毎時800個の商品が作れる包あん機「MHS-1」や和菓子・洋菓子、惣菜など様々な食品加工に対応した「SR-7S」を紹介するので、最後までお読みください。
小型の包あん機とは?

小型の包あん機とは、その名の通り従来よりもコンパクトなサイズで設置場所を選ばず使える包あん成形機のことです。
少量多品種の生産に最適な多用途モデルもあり、手狭なスペースでも手軽に導入できるのが特長です。
例えば株式会社コバードの小型機ラインアップでは、毎時約800個から最大14,400個までカバーしています。
大型機に比べ処理能力は抑えめな分、本体サイズが小さく設置しやすい利点があります。
中には卓上サイズの超小型モデルも存在し、小規模工場や店舗の限られたスペースでも活躍します。
小型の包あん機で生産できる食品
サイズは小さくても、製造できる製品の幅広さは大型機に劣りません。
和菓子であれば栗饅頭、柏餅、桜餅などの餅菓子・饅頭類から、おはぎや月餅、中華まんじゅうまで対応可能な機種があります。
機種によっては餡やクリームだけでなく、栗や卵、ソーセージといった大きめの具材も同時に包み込むことも可能です。
また、つみれやミートボールといった惣菜にも対応しています。
小型の包あん機が向いているシーン

小型の包あん機が向いているシーンは以下の通りです。
- 商品のバリエーションが多く頻繁に切り替わる現場
- 設置スペースが限られている現場
小型包あん機は製品バリエーションが多く頻繁に切り替わる現場に特に適しています。
季節限定の和菓子や洋菓子など、充填する餡や具材をしょっちゅう変更する場合でも、小型機ならセッティング変更にかかる手間が比較的少なく効率的です。
モデルによってはフィリングを入れるホッパー(シリンダー)がカセット式になっており、材料交換が簡単に行えるためスムーズに製品の切替えができます。
スペアのホッパーごと冷蔵保管しておけば、次の仕込みへの段取りも素早く行えるでしょう。
また、設置スペースが限られている場合でも小型包あん機は力を発揮します。
厨房や売り場の一角など導線を圧迫しないスペースに収まる超小型モデルもあり、狭いバックヤードでも無理なく稼働可能です。
例えば卓上サイズの機種であれば作業台の上に載せて店頭実演に使うこともでき、できたての商品を提供するサービスにも最適です。
省スペース性と機動力の高さから、イベント出店や移動販売など限られた空間での製造にも対応しやすいでしょう。
コバードが提供する小型の包あん機
弊社の小型包あん機の代表例として、MHS-1(マジックハンドスマート)と、SA-7S(SMALLロボセブン スーパー)があります。
MHS-1(マジックハンドスマート)

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 生産能力 | 最大800個/時 |
| 製品重量 | 35g〜160g(1個あたりの製品重量) |
| 外形寸法 | 全幅1,435mm × 奥行835mm × 高さ1,448mm |
| 電源容量 | 三相200V、1.5kW |
| 空気使用量 | 40 Nℓ/分 |
| 標準商品形状 | 丸形(※リーフ形、パーカー形はオプション対応) |
| 主なオプション | リーフ形成形ユニット、パーカー形成形ユニット、リターンコンベア、ポケットモルダー 等 |
上記の通り、MHS-1は最大800個/時の生産能力を持ち、35〜160g程度の商品サイズに対応しています。
寸法は幅1.4m強と省スペースで、可動式キャスター付きの据え置き型ながら狭いスペースでも取り回しやすい設計です。
オプション装着により、標準の丸形以外にもリーフパン(葉っぱの形をした成形パン)やパーカーロール形状の包あん成形にも対応可能となっており、汎用性も備えています。
発酵生地特有の柔らかさや伸展性に配慮した独自構造のおかげで、菓子パン、生クリームを包んだデニッシュ、ドーナツや中華まんなど手包み以上の本格的な製品を安定して製造できる点が評価されています。
SA-7S(SMALLロボセブン スーパー)

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 生産能力 | 最大1,200個/時 |
| 製品重量 | 10g〜70g(1個あたりの製品重量) |
| 外形寸法 | 全幅805mm × 奥行627mm × 高さ850mm / コンベアの高さ300mm |
| 電源容量 | 3P 200V 0.5kw |
| ホッパー容量 | 6ℓ |
| 標準商品形状 | 球状、俵状、棒状、連続吐出 |
SA-7Sは、超小型ボディと軽量設計で、省スペースでも設置できるため小規模工場や店頭実演に最適です。
生産能力は最大1,200個/時を誇り、10〜70gまで幅広い製品サイズに対応しています。
例えば、おはぎや餅アイス、ガナッシュチョコレートやチュロスといった和菓子・洋菓子だけでなく、胡麻団子やニラ饅頭、メンチカツやコロッケといった総菜にも対応しています。
操作はカラー液晶タッチパネルで直感的に行え、最大100種類のレシピを登録できるので、多品種・小ロット生産もスムーズです。
IoTにも対応しており、メンテナンスや点検も遠隔で管理できるので安心して運用できます。
小型の包あん機を導入する際のチェックポイント
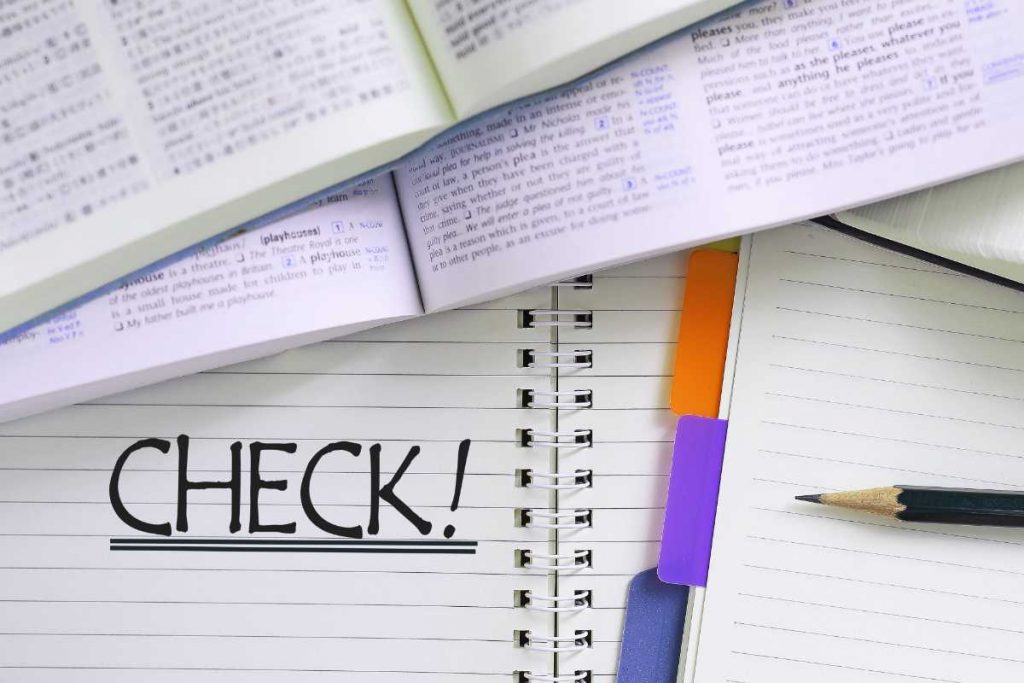
小型包あん機を導入するにあたっては、事前にいくつかの重要ポイントを確認しておく必要があります。
ここでは「設置・搬入条件」「衛生面の管理」「取り扱う製品特性」の観点からチェック事項を解説します。
設置・搬入条件の確認
- 設置スペースの確保:本体寸法と周囲の作業スペースが十分か確認
- 搬入経路の確認:間口や段差、障害物やエレベーターのサイズ・耐荷重をチェック
- 環境条件への対応:機械稼働時の排熱や騒音に適した設備の必要有無の確認
- インフラの確認:床の耐荷重、電源(電圧・容量)、エアー源の有無を確認
分解洗浄と衛生設計
- 分解のしやすさ:自身で洗浄できるように分解しやすい構造か確認
- 洗浄の手間:分解した部品が洗浄しやすいかを確認(水洗い可能など)
充填物・生地特性の適合
- 食材の適合性確認:餡の粘度や水分量、具材の大きさ、生地の特性が機械の仕様に合っているか確認
- デモンストレーションの実施:実際に使用する食材でテスト加工を行い、問題なく成形できるか検証
- オプション仕様の検討:食材に合わせてオプション仕様が必要か検討
小型包あん機の価格と契約形態
小型包あん機の導入コストは決して安くありませんが、その支払い方法や新品中古の選択によって負担の度合いが変わってきます。
初期投資(一括購入費用)と月次キャッシュフローのバランスを考慮し、購入かリースか、新品か中古かを検討することが大切です。
中古市場を調べると、機種や状態によっては数百万円クラス(数十万円~数百万円)の出品も見られ、賢く選べば初期費用を大きく抑えられる可能性もあります。
買い切りかリースか
包あん機を買い切り(直接購入)する場合、導入時に多額の資金が必要になりますが、その後のランニングコストはメンテナンスや部品交換費用程度に限られます。
減価償却による資産計上も可能となり、長期的には所有権が手元に残るメリットがあります。
一方、リース契約を利用すれば初期の出費を抑えて月々定額の支払いで導入できます。
リース料には保守サービスが含まれる契約もあり、機械の故障リスクに備えやすい利点もあります。
しかしトータルではリース金額の方が高くつくことが多く、契約期間中は解約しづらい制約もあります。
新品か中古か
新品機の購入は初期費用が高めですが、最新機能や性能の恩恵を受けられ、メーカー保証やアフターサポートも手厚いという安心感があります。
特に衛生面や省エネ性能、操作性などは新機種ほど改善されている傾向があるため、予算に余裕があれば新品導入が望ましいでしょう。
一方で中古機は購入価格を大幅に抑えられる点が魅力です。
数百万円クラスの新品に比べ破格ですが、その分整備状況や残存寿命については十分注意が必要です。
小型の包あん機を導入する際の注意点

最後に、小型包あん機を導入・運用する上で陥りがちな注意点を紹介します。
現場のシミュレーション不足
生産計画の詰めが甘いまま機械を導入すると、宝の持ち腐れになりかねません。
例えば必要以上に高性能な機種を入れても、生産量が少なければ機械の稼働率は上がらず、清掃や段取り替えにかえって時間を取られる恐れがあります。
導入前に現場での稼働シミュレーションを行い、1日の生産サイクルやロットサイズに対して適切な能力の機械を選定することが重要です。
械を使えば1時間に数千個作れるとしても、実際には仕込みや後片付けの時間が必要になります。
衛生・洗浄のメンテナンスの複雑さ
機械導入後に意外と効いてくるのが日々の衛生管理にかかる手間です。
前工程・後工程の清掃時間や人員をきちんと見積もっておかないと、「機械では作業自体は速くなったが、洗浄に時間がかかり結局トータルの効率が上がらない」という事態にもなりかねません。
特に餅やパン生地など粘着性の高い素材を扱う場合、機械内部に生地片や餡が残りやすく、徹底した洗浄が欠かせません。
洗浄箇所が多かったり分解に時間がかかる機械だと、想定以上に洗浄作業に人手と時間を取られることがあります。
実運用をイメージし、例えば「1日の生産終了後30分以内で洗浄完了できるか」「週次の分解清掃に何時間必要か」など具体的な基準で評価しましょう。
充填物の物性不一致
機械と素材のミスマッチにも注意が必要です。
導入後に「思っていた製品がうまく作れない」というトラブルの多くは、生地や中身の性状が機械特性に合っていないことに起因します。
たとえば具材の粒が大きすぎてノズルに詰まってしまったり、生地が硬すぎてうまくシール(閉じ合わせ)できなかったりするケースです。
これを防ぐには、導入前の段階で作りたい製品に合わせた実機テストを繰り返し行い、問題点があれば機種変更やカスタマイズで解決することが重要です。
必要に応じて、餡の粒度を調整したり、生地の配合(水分量や油脂量)を機械対応しやすい範囲に見直す検討も有効でしょう。
また、メーカー側に相談すれば「〇〇用特別仕様」のように素材に合わせた専用機やオプションを提案してもらえる場合もあります。
実際、非常に扱いにくい素材でも独自の工夫で対応できる機種がありますが、逆に言えば機械の標準仕様では難しい製品もあるということです。
「何でも包めるだろう」と過信せず、事前確認と適切な機種選定を怠らないようにしましょう。
まとめ
少量多品種生産や省人化ニーズの高まりを背景に、小型包あん機は和菓子や洋菓子、惣菜を中心に存在感を増しています。
従来は人手に頼っていた繊細な包あん作業も、コンパクトな機械で自動化することで生産効率と品質の両立が可能になりました。
特に省スペースで柔軟に運用できる点は、小規模事業者や店舗併設の工房にとって大きなメリットです。
小型包あん機の導入をご検討中でしたら、ぜひ一度、株式会社コバードの機械をご覧ください。